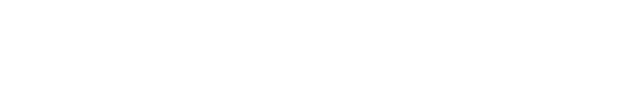漢方薬という選択肢
●はじめに
漢方と聞くと、「本当に効くの?」、「苦くて飲めないんじゃない?」とあまり良いイメージをお持ちでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、半信半疑で試して意外と効果を感じられるケースもあります。
当院でも患者様と相談の上、処方させていただく事もあります。
今回はそんな漢方薬について、使用例や注意点も含めて(簡潔ではありますが…)ご説明させていただきます。
●漢方が考えるカラダのしくみ
漢方治療の原則は「カラダの働きを正常に戻す」こと。健常時は我々のカラダは正しい生理活動(カラダの恒常性の維持)をしていますが、それが崩れると病気になります。それを健康な状態に戻そうとするのが漢方治療です。
また漢方において健康な状態とは、気(エネルギー)・血(潤し養う)・水(潤し冷やす)が正しく巡り、臓腑を正しく動かすことで生命を維持していると考えます。
●漢方使用例
①感冒・・・葛根湯(かぜのひき始め)、麻黄湯(発熱、関節痛)、麻黄附子細辛湯(冷え、悪寒)、小青竜湯(鼻水、くしゃみ)、etc.
②咳、痰・・・麦門冬湯(喉にはりついた痰、咳)、柴朴湯(痰がらみの咳)、清肺湯(痰が多い咳)、小青竜湯(水様痰、鼻水、くしゃみ)、etc.
③疲労倦怠感・・・補中益気湯(気力がわかず疲れやすい)、人参養栄湯(高齢で体力が著しく低下)、十全大補湯(貧血気味)
④手足の冷え・・・当帰四逆加呉茱萸生姜湯(しもやけ、冷えて痛み)、当帰芍薬散(冷えてむくみ)、牛車腎気丸(加齢に伴う下半身の冷え)
⑤食欲不振・・・六君子湯
⑥下痢・・・半夏瀉心湯(ゴロゴロなるお腹)、五苓散(水瀉性下痢)
⑦便秘・・・防風通聖散(太鼓腹で便秘)、麻子仁丸(高齢者のころころ便)
⑧腹部膨満感・・・大建中湯⑨肩の症状・・・葛根湯(肩こり)、二朮湯(五十肩)
⓾こむら返り・・・芍薬甘草湯
⑪咽頭痛・・・桔梗湯、小柴胡湯加桔梗石膏エキス
⑫残尿感、排尿痛・・・猪苓湯
⑬頻尿、排尿困難・・・牛車腎気丸
⑭打撲・・・治打撲一方
⑮月経不順、月経困難、更年期障害・・・当帰芍薬散(冷え性、貧血傾向)、加味逍遥散(イライラなど精神神経症状強い)、桂枝茯苓丸(体格がっちり、のぼせ傾向)
等々、まだまだ沢山の選択肢が存在します。
●注意点
現在使用されている医療用漢方製剤148品目のうち109処方(約70%)にカンゾウ(甘草)が含まれています。この主成分であるグリチルリチン酸は副腎皮質ホルモン様の作用があり、偽アルドステロン症(低カリウム血症、血圧上昇、体液貯留による浮腫、等)が認められることがあるため、十分な経過観察が必要であるとともに不必要な長期乱用は避けるべきと考えます。
また、生薬の麻黄が含まれている漢方には交感神経刺激作用のあるエフェドリンが含めれており、胃腸虚弱や高血圧、心疾患の既往がある患者様への投与は慎重に行います。
気になられている症状があれば、是非当院にご相談ください。また公立図書館にも漢方に関する書籍は意外と所蔵されておりますので、参考にしていただければ幸いです。